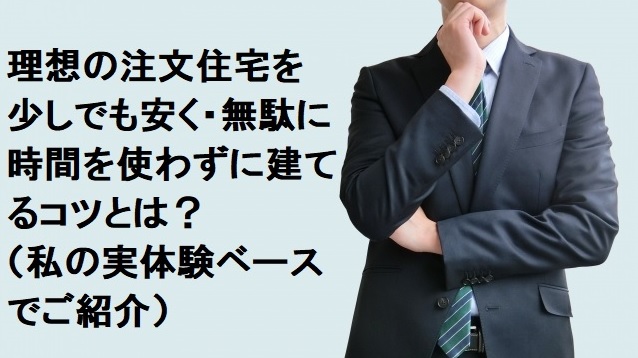ハウスメーカーの坪単価比較ランキング(最新情報)に意味がない本当理由!
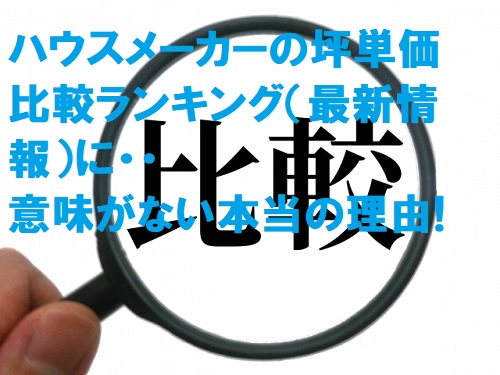

村上悠です。
自宅を三井ホームで、賃貸の平屋のガレージハウスを工務店で建てた経験があります。
もともと家づくりが好きで、かなり研究もしました。
こういった実際の経験をベースに記事を書こうと思います。
注文住宅を建てる場合、当然ですが、坪単価、費用がどれくらいかかるのか、気になります。
特にハウスメーカーで建てる場合は、各社が坪単価を公表しているので、余計、気になります。
ネットで検索してみると、各ハウスメーカーの坪単価を比較する一覧情報が、本当に多く見つかります。
実は、私も、三井ホームで自宅を建てる際に、さんざん坪単価について調べました。
自分の経験から、よくわかるのですが、ネットで検索されるハウスメーカーの坪単価情報、特にランキングは、そのまま信用しない方がいいです。
これから、なぜ、意味がないと思うのか、その根拠を3つお話します。
これから新築をお考えの方には、きっと役に立つと思います。
最後までお読みいただければと思います。
ハウスメーカーの坪単価比較ランキング(最新情報)に意味がない本当の理由3つ

なぜ、ハウスメーカーの坪単価比較ランキング(最新情報)が意味がないと考えるのか、本当の理由3つを解説します。
(1)そもそもハウスメーカー坪単価の一覧情報の金額がバラバラであるから。
(2)各ハウスメーカの坪単価の計算根拠がバラバラであるから。
(3)坪単価を明確にいくらと言い切ることに無理があるから。
(1)そもそもハウスメーカー坪単価の一覧情報の金額がバラバラであるから。
私は、現在の自宅を、三井ホームで建てましたので、その三井ホームについての坪単価について調べてみました。
ハウスメーカーの坪単価の比較ランキングをいくつか確認した結果です。
| (A)坪単価ランキング | (B)坪単価ランキング | (C)坪単価ランキング |
|---|---|---|
| 70万~90万円 | 71万円以上 | 75万~90万 |
三井ホームの場合は、金額はバラバラですが、何となく、70万円~90万円程度なのかというのが、わかります。
次に、ミサワホームについて確認してみました。
| (A)坪単価ランキング | (B)坪単価ランキング | (C)坪単価ランキング |
|---|---|---|
| 65万~90万 | 61万~70万 | 65万~75万 |
ミサワホームの場合は、最低坪単価は、おおよそ一致しておりますが、最高坪単価が、70万円だったり、90万円であったり、大きく金額が異なります。
このように、ハウスメーカーの坪単価ランキング情報によって、金額が大きく異なり、正直、ここまで金額が違うとなると、意味がないと思います。
もう一つ、今度は大和ハウスについて見てみます
| (A)坪単価ランキング | (B)坪単価ランキング | (C)坪単価ランキング |
|---|---|---|
| 65万~75万 | 61万~70万 | 55万~80万 |
大和ハウスの坪単価も、かなり金額にバラツキがあります。
ここまで金額が違うとなると、これらデータを信用して進めた場合、とんでもないことに。
なぜ坪単価が、ここまで金額が大きく異なるのか・・それには、明確な理由があります。
その理由は、次の(2)と(3)で解説します。
(2)各ハウスメーカの坪単価の計算根拠がバラバラであるから。
実は、各ハウスメーカーが公表する坪単価の計算根拠が同じではありません。
各社それぞれの考え方や方針によって、坪単価を決めています。
各社異なる計算根拠で、算出した坪単価を、比較する意味がないわけです。
さらに詳しく解説します。
通常、「坪単価」と言えば、 「建物の本体価格」を「延床面積」で割った数値のことです。
これが当然のことであり、各ハウスメーカーも皆、同じであると思われていませんか?
しかし・・そこが違います。
実は、「建物の本体価格」を「延床面積」ではなく「施工面積」で割った数値とするというハウスメーカーがいます。
「施工面積」には、「延床面積」には含まれない、床がない吹き抜け部分、玄関ポーチ、ロフト、ベランダやバルコニー(外壁面からの突出幅が2m以下の部分)などが含まれます。
つまり、「施工面積」の方が「延床面積」より、その分広くなります。
なので、より広い「施工面積」で割る「坪単価」の方が、当然、安くなります。
ちなみに、これは違法なことではありません。
建築基準法で規定されているのは「建築面積」と「延床面積」の2つだけで、両者の計算根拠になるのが「床面積」です。
ここは、法律が要求することなので、それぞれ、厳密な計算方法が適用されます。
この延床面積を偽ると、それは建築基準法上、違法です。
しかし、それ以外の例えば「施工(床)面積」といったものは、何も、法律に定められておりません。
法的厳格なものではなく、計算の仕方も違えば、その意味するところも全く異なります。
各ハウスメーカーや工務店が、独自のルールを定め運用しています。
坪単価を計算するのに、建築費用をだす際の目安として、この「施工(床)面積」を「延床面積」として使っているだけです。
「延床面積」で算出した坪単価と「施工面積」で算出した坪単価が異なるのは当然です。
この異なる基準により算出した坪単価は、そもそも比較する意味がないのです。
通常、「坪単価」と言えば、 「建物の本体価格」を「延床面積」で割った数値のことです。
これは、先ほどお話しました通りです。
その 「建物の本体価格」に、そもそも、含めるのか否かが、各ハウスメーカーによって異なります。
例えば、照明器具とか、エアコンは本体価格に含めるのかといったケースです。
ここも、ハウスメーカーによって、扱いは異なります。
当然、こういった費用を本体工事費用として、建物の本体価格に加えていけば、その分、坪単価は高くなります。
本体工事費用にどこまで含めるのかも、各ハウスメーカーで異なります。
(3)坪単価を明確にいくらと言い切ることに無理があるから。
各ハウスメーカーは、1社で様々な住宅商品を販売しています。
商品によって、坪単価に、かなりひらきがあります。
例えば、こちらの住宅産業新聞の記事です。
大和ハウス工業で、九州7県で坪単価100万~200万円の木造フルオーダーの受注を始めたというニュースです。
最高級の住宅を富裕層に販売する計画とあります。
この富裕層向けの商品の坪単価は、先程の大和ハウスのデータでは、対象外とされています。
| (A)坪単価ランキング | (B)坪単価ランキング | (C)坪単価ランキング |
|---|---|---|
| 65万~75万 | 61万~70万 | 55万~80万 |
各ハウスメーカーでは、住宅商品ラインナップが多く、様々な商品を扱っております。
いったいどこまでの商品の坪単価を、ランキングの対象にすべきなのかが、今度は、ランキングを作成する側で異なります。
まず、坪単価の算出根拠が、ハウスメーカー各社によって異なり、
さらに、今度は、各社の販売する住宅商品の、どこまでを坪単価ランキングの対象とすべきか、今度は、ランキングを作成する側で考え方が異なります。
このようなことから、ハウスメーカー坪単価ランキングを、そのまま信頼するのは、危険だということです。
ハウスメーカーの坪単価は、あくまでも一つの目安と考えるべき
ハウスメーカー坪単価のまとめ
以上の説明から、ハウスメーカーの坪単価ランキングを、比較検討する意味がないことが、よくおわかりいただけたと思います。
では、新築を検討される際には、まずどうしたらいいのでしょうか?
それは、まず坪単価から、ハウスメーカーを絞ってしまうのではなく、幅広く、検討されることをおすすめします。
まずは、どういう家に住みたいのか、家族でよく話し合い、理想とする住まいのイメージを持ちます。
(ここは、リフォームをする場合と同じです。)
次に、そのイメージを、各ハウスメーカーにぶつけてみます。
その際に、いくらくらいで建てたいのか、予算も条件として提示します。
各ハウスメーカーから提示のあったプランを検討し、進めればいいのです。
こちらを利用されては、いかがでしょうか。
↑ ↑
こちらをクリック!!

著者情報:
村上悠
レリッシュプラン株式会社:代表
経営するRCマンション、平屋ガレージハウス等、複数の賃貸物件について、空室対策として何度もリフォームを行ったことがあります。
リフォームは、室内のクロス、床、天井といった小規模なものから、屋根や外壁をリフォームする大規模修繕の経験もあります。
また、自宅を三井ホームで建て、さらに賃貸物件の平屋ガレージハウスを建てる等、新築の家づくり経験もあります。
そういったリフォームや家づくり経験で得た気付き、知識等を、記事にしていきたいと思います。
リフォームや家づくり等に役立つであろうと、資格も取得しました。
賃貸業など不動産ビジネスに役立つであろうと、宅地建物取引士に2008年に合格。
また、家づくり、リフォームに色彩は重要ということで、2級カラーコーディネーター(商工会議所)の資格を2019年に取得。
さらに、以前サラリーマン時代に、国内旅行業務取扱管理者の資格も2016年に取得。